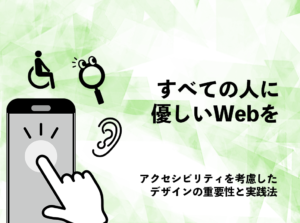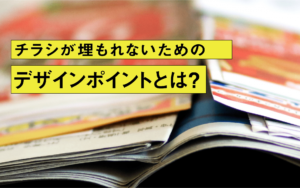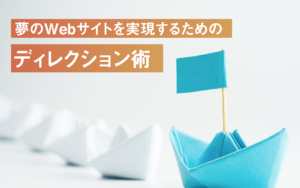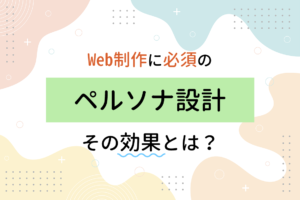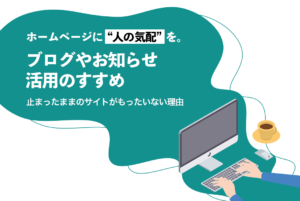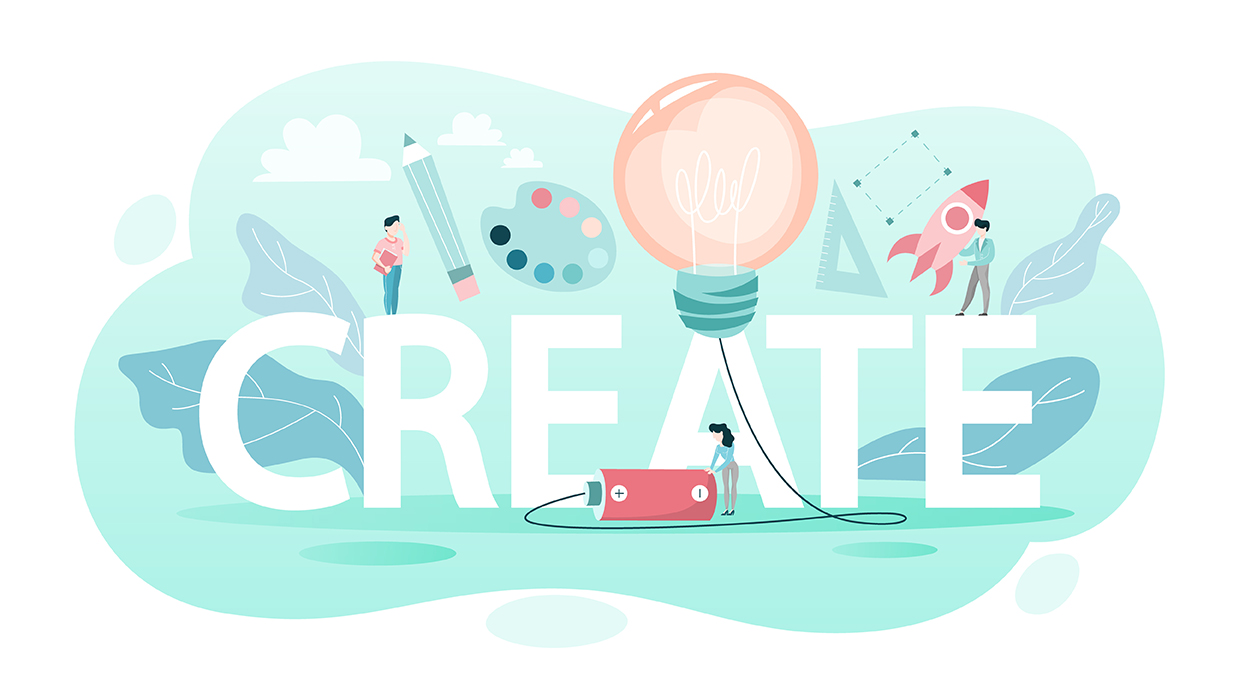を提供するパートナー


「納期が守れるプロジェクト」に変える方法|Webディレクターができる工夫とは?
- マーケティング
更新日
2025.10.17
公開日
2025.10.17
Contents
Web制作の現場でよくある悩みのひとつが、「スケジュール通りに進まない」「納期がズレる」問題。
実はこの原因、制作側だけでなく、依頼側にもあることが多いんです。
今回は、Web制作がスムーズに進まない本当の理由と、それを防ぐためにできる対策・ディレクターにできることをわかりやすく解説します。
「資料の提出が遅れる」問題
Web制作に必要な素材(テキスト、写真、ロゴデータなど)がそろわないと、
作業がストップしてしまいます。
ありがちなケース
・「原稿、少し時間ください」が1週間伸びる
・「この写真で大丈夫ですか?」と確認→返事が遅れる
・ロゴデータが印刷用しかなく、Web用を探すのに時間がかかる
対策
・初回打ち合わせ時に「いつまでに何を提出すべきか」リストで共有
・画像やロゴはできるだけ編集可能な形式(ai / psd / pngなど)で
・参考になる既存資料があれば、たとえラフでも早めに出す
★ ディレクターができること
・初回ミーティングで“提出物一覧チェックリスト”を作成・配布
・各素材について「まだですか?」ではなく、リマインド+サポート(例:原稿の構成を一緒に整理する、画像選定のルールを提示する)
・「なくても進められる範囲」「仮素材での進行可否」を判断し、全体スケジュールに柔軟性をもたせる
「確認&修正に時間がかかる」
デザインの確認や原稿のチェックで、社内での意思決定がスムーズにいかないことも遅延の要因です。
ありがちなケース
・担当者が確認したが、後から上司がNGを出す
・社内で決裁者が多く、何度も戻ってくる
・修正点が曖昧 or 後出しで「やっぱりこうしてほしい」が多発
対策
・決裁者を明確にし、確認フローをシンプルに
・フィードバックはまとめて一括で(小出しはNG)
・修正の範囲が大きい場合は納期の再調整が必要と認識しておく
★ ディレクターができること
・プロジェクト開始時に「誰が確認し、誰が最終OKを出すか」を可視化・共有
・修正依頼の出し方をテンプレート化し、具体的に書いてもらう(例:「◯ページの◯◯という文言を◯◯に変えてください」)
・複数案を提示することで「ジャッジしやすくする」工夫
・修正範囲が想定を超える場合は、“納期と費用”の再調整提案を事前に伝える
「イメージが固まっていない」
依頼時点で「とりあえずおまかせで」というスタンスだと、方向性のズレや認識の違いが発生しやすくなります。
ありがちなケース
・完成してから「なんか思ってたのと違う…」
・好きなテイストが定まっておらず、デザイン修正が何度も発生
・「競合のサイトを見て、やっぱりこうしたい」が途中で出てくる
対策
・初回ヒアリング時に「参考サイト」を複数出してもらう
・ざっくりでいいので、「雰囲気」「色味」「トーン」の希望を事前に共有
・要望が後から変わる可能性があるなら、それも先に相談
★ ディレクターができること
・デザインヒアリングシートを使って、好みやNG要素を明確にする
・「こういうのが合いそう」と提案ベースで参考例を出す(PinterestボードやNotionリンクなど)
・後から要望が出そうな場合に備えて、「初回提案時点では〇パターンまで」と設計のルールを明確にする
「制作側・依頼側の温度差」
「急ぎで作りたい」と言いつつ、返信が2〜3日後…というケースも多くあります。
対策
・緊急時の連絡手段」や「週1で進捗を共有する時間」を確保する
・制作側だけが焦って進めても、うまくいかないことをお互いに理解する
★ ディレクターができること
・定期的な進捗レポート(週報やチェックリスト)を送付して安心感を与える
・最初に「〇日以上返信がない場合、どう判断するか」をルール化しておく
・ツール(SlackやChatwork、Notionなど)を使って、ステータスの見える化をすることで“温度感”を揃える
実は「納期=公開日」ではないこともある
Webサイトは「完成=公開」ではなく、公開日から逆算して準備が必要です。
・狙ったタイミングで広告・SNS連携をしたい
・イベントやキャンペーンと合わせて公開したい
・ドメイン設定やSEO施策にも時間がかかる
対策
・ゴール(公開日)から逆算してスケジュールを組む
・“なんとなく”ではなく、目的ありきで制作に入る
★ ディレクターができること
・公開日ありきで全体スケジュールを逆算したガントチャートを作成・共有
・「公開した後に何をするのか?」(告知、広告、運用)まで含めた全体像を共有
・公開準備(サーバー設定、フォームテスト、OGP、アクセス解析タグなど)も段階的にチェックリスト化して管理
まとめ|Web制作は「共同作業」
納期遅延の多くは、制作側・依頼側の“すれ違い”で起こります。
Web制作は、「お願いしたら全部やってくれる」という一方通行ではなく、
お互いにゴールを共有して、協力して進める共同作業です。
プロジェクトをスムーズに進めるためには、
「誰が、いつまでに、何をするのか」を明確にし、
レスポンスのスピード感を合わせていくことが重要です。
また、Web制作を円滑に進めるためには、
「素材の有無」や「イメージの共有」など、細かな要素が複雑に絡み合います。
でも、それらを見える化・仕組み化・テンプレ化して、依頼者と並走するのがディレクターの役割。
「ただ進行管理をする人」ではなく、
「制作チームと依頼者の橋渡し役」としての存在が、
結果的に納期を守る最大のポイントになるのかもしれません。